
“食”を通して、安心を届けるしごと
トップフードのお仕事について教えてください
菊地さん:弊社は、いわゆる「調理済み食材」を提供している会社です。
対象になるのは、病院だったり、老人ホームだったり、毎日誰かに食事を出さなきゃいけない現場。
学校給食は少し違うんですが、医療・福祉系の施設が主なお客さまになります。
「調理済み食材」と聞くと、お弁当と捉えられがちですが、お弁当は基本的に常温で届けられてることが多くて、温度管理が甘いケースも少なくない。
だから、ノロウイルスのような食中毒の原因になることもあるんです。実際、全国的にそういう事故って今もありますよね。
うちが提供してる食材は、調理したあと急速冷却をして、袋詰めしてお届けしています。
施設ではそれを温め直して提供してもらう形になるので「安心して食べられる」というのが最大の価値だと思っています。
富山県内だけではなく、実は全国配送しています。
北は北海道から南は九州まで、どこにでもうちの商品が届く体制になってます。
拠点自体は富山にありますが、ありがたいことに、他社さんからうちに切り替えてくださるお客さまも多くて。
数字で断言できるものではないですが、富山県内のシェアはもちろんの事、全国的にもそれなりにあると思います。

“人が足りない現場”に、自分ができることを
なぜ富山で事業を始めたのでしょうか?
菊地さん:私が前職で働いていたのは給食業でした。
日々感じていたのは、「とにかく人が足りていない」という現実です。
朝3時から仕込みに入って、夜9時まで洗い物――ほとんど一日中、現場で動きっぱなし。
これを何年も続けていくのは、本当にしんどい。
でも、どれだけ現場が悲鳴を上げても、「今まで通りやってください」で終わってしまう。
私はその矛盾を、目の前で見てきました。
じゃあ、自分に何ができるか考えたとき、「調理済み食材」という選択肢に行き着きました。
湯煎して盛り付ければ完成。調理員の負担を減らしつつ、安心・安全の食を提供できる。
でも、それを現場に導入してもらうには、“価格”という壁を越える必要がありました。
そんなとき、とある工場と出会ったんです。
もともとスーパー向けにお惣菜を大量に卸している大規模な工場で、日々何万食という単位で製造しているため、食材の仕入れ価格や生産効率が段違いなんです。
たとえば、にんじんを10本仕入れるのと、1万本仕入れるのでは、1本あたりの価格がまったく違う。
そうしたスケールメリットを活かして、私たちのオリジナル献立をOEMで作ってもらえるよう、直談判しました。
結果、うちが小さな工場で手作りするよりも、圧倒的に低コストで品質の高い商品を提供できる体制が整ったんです。
そこで一気に道が開けましたね。
生産コストを抑えながら、品質を保ち、現場の負担を減らせる。
自分が事業をはじめたきっかけは、本当にシンプルでした。
「困ってる人がいるなら、何かしたい」それだけなんです。

「働くってなんだろう」を、ずっと問い続けている
事業運営の中で苦労している事はありますか?
菊地さん:会社を大きくしていくうえで、一番苦労しているのは「人材集め」です。
上を目指すには、人の力が必要。でも、その“人”って、誰でもいいわけじゃないんですよね。
最初の頃は本当に苦労しました。
SPIみたいな適性検査を導入して、面接だけじゃわからない部分も丁寧に見ようとしていました。
小さな会社でそんなことをするのは珍しいかもしれません。
でも、こちらとしても“誰でもいいわけじゃない”ですし、相手にとっても“間違った選択”になってほしくない。
お互いにとって良い選択になるよう、時間も手間もかけてきたつもりです。
それでも、やっぱりズレは出てきます。
入ってみて、色々ありますよね。「あれ、違うな」って言ってすぐやめるというようなことは。
うちは少数精鋭でやっているから、大手みたいに「この仕事だけやっていればOK」っていう働き方は正直難しいんです。
いろんなことに手を出さないと回らない。だから、一人ひとりにかかる責任もあるし、そのぶん信頼も深い。
“少数精鋭”というのは、ただ人数が少ないという意味ではなくて、
一人が一人以上の力を出して、お互いに補い合っていけるようなチームであること。
だからこそ、売上が伸びたときに、1.5人必要な仕事を1人で補えば、そこで余った利益をそのまま1人の従業員に還元できる。
それが、うちのやり方なんです。
とはいえ、少子高齢化はもう何年も前から叫ばれているけれど、現場での実感は年々深刻さを増していて
「このままじゃ、回らないな」って肌で感じることが、本当に増えてきました。
だからこそ、働き方を見直す必要があると思うんです。
「どうすれば、長く、無理なく働き続けてもらえるか」
「どうすれば、“ここで働いてよかった”と思ってもらえるか」
その答えを探すのが、今の私のいちばんの仕事かもしれません。
地方にいるからこそ、県外にもに目を向けて、外の売上を富山に還元する。
そういう循環も必要だと思っています。
人は“人材”ではなく“人財”。働いてくれる人こそ、会社の未来をつくる最大の資産です。
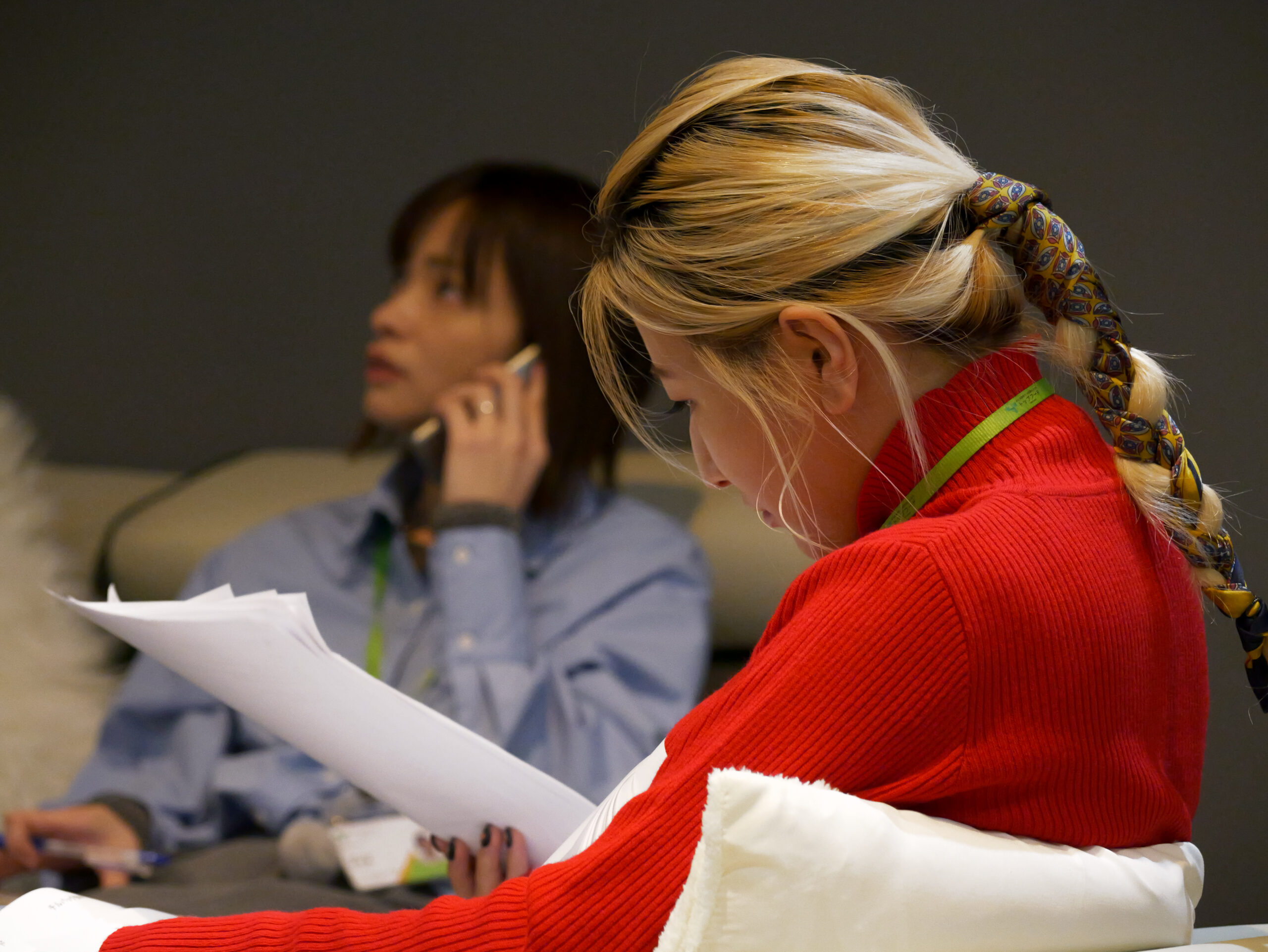
“このままでいいや”じゃ、変わらない。だから、うちがやる。
すごくオシャレなオフィス環境ですよね
菊地さん:このオフィス、特別おしゃれにしようと思って作ったわけじゃないんです。
私が一番考えていたのは、「従業員が気持ちよく働ける場所にしたい」ということでした。
給食業界って、どうしても古い体質が色濃くて、環境も昔ながらのまま。
建物も設備も、昭和のまま止まってるような現場もまだまだ多いんですよね。
特に女性が多い業界なのに、「選びたくなる職場」がないっていうのは、すごくもったいないことだと思っていて。
だったら、うちがその“選択肢”をつくればいい。そう思って、今の環境を整えました。
たとえば「美容手当」もうちの福利厚生の一つです。
前職では、厨房で働く女性たちが、髪型すら自由にできないような職場も多かった。
ネイルもNG、ヘアカラーも制限される。
でも、ネイルだって、髪型だって本人が生活する中ですごく大切な要素ですよね。
「厨房では帽子をかぶるのに髪型を制限する意味って何だろう」とかそういった制限に違和感を感じてきました。
だから、うちでは「ネイルもOK」「髪型も自由」。
そのうえで、好きなネイルを楽しんでもらえるよう、美容手当を出しています。
それだけで「ここで働いてて楽しい」って思ってもらえるなら、やらない理由はありません。
「人を大切にしたい」それは、私自身が「職場にそうしてもらいたかった」からですね。
富山の中に少しでも「ここで働いてみたい」と思ってもらえるような会社を増やしたい。
うちがそのひとつになれたら、そんなに嬉しいことはありません。


“トップフード”という名前が、当たり前に聞こえる未来へ
これからの展望として、どんな未来を目指していますか?
菊地さん:全国展開といっても、正直まだまだうちの知名度は低いです。
各都道府県に数施設ずつ取引先がある、というレベル。
正直、まだ“始まったばかり”の会社だと思っています。
でも、私はいつか「調理済み食材といえばトップフード」と言ってもらえるような、そんな存在になりたいんです。
そのためには、まず「知ってもらうこと」。
いくら価格が安くて、品質も良くて、現場の負担が軽くなるものだとしても、そもそも“知られていなければ、選ばれることもない”。
だから、これからは広報や情報発信にももっと力を入れていきたいと思っています。
富山って、若い人が県外に出ていきがちじゃないですか。
特に女性の転出率は全国で見ても高くて「いい会社が富山にないから出ていく」っていうイメージを持たれがちなんですよね。
でも、それって“知らないだけ”なんじゃないかと思うんです。
ちゃんと目を向ければ、富山にも「ここで働きたい」と思える会社がある。
小さな会社かもしれませんが、やれることはまだまだたくさんあると思っています。
だからこそ、まずは知ってもらう。富山から、もっと外へ。
その積み重ねが、未来のトップフードをつくっていくんだと思っています。

「自分にとっての“いい会社”」は、探せばちゃんと見つかる
これから就職を控える若い世代へ、エールやメッセージをお願いします。
菊地さん:若い方に何か偉そうなことを言える立場じゃないんですが……それでも、ひとつだけ伝えたいのは、
「いま自分がいる場所の“いいところ”を探してみてほしい」ということです。
隣の芝生は、いつだって青く見えるもので。
SNSを見れば都心のキラキラした会社や、楽しそうな働き方が次々に流れてきます。
でも、実は自分の足元にも、“本当はいい場所”があるかもしれないんですよね。
もちろん、一社に固執しなくていいと思います。
いろんな会社を知って、比べてみて、自分にとっての“心地いい場所”を見つけていけばいい。
私自身もいろんな環境を見てきました。だからこそ、いま「ここがいい」と思える場所にいる実感があります。
一度外に出てみるのもいいし、富山の中をもっと深掘りしてみるのもいい。
大事なのは、“比べた上で選ぶこと”なんだと思います。
自分にとっての「ここがいいな」が見つかれば、働くってきっと面白くなる。
そんな出会いを、焦らず、ゆっくり見つけていってほしいなと思います。

▽取材先企業情報▽
株式会社トップフード
〒939-0332
富山県射水市橋下条2024番地
TEL:076-654-0776
HP:https://topfood.jp/company/
ライター:長谷川 泰我

